1200年の伝統ある街「京都」。戦災の影響も少なく、歴史ある街並みが残る都市ですが、古い建築物はどんどんと少なくなり、中心部ではマンション、郊外では現代的な住宅が増えています。
そんな京都で、今、とても人気のある物件が京町家です。間口が狭く、奥行きが深い、うなぎの寝床と呼ばれる京都独自の町家が、住居としてだけではなく、店舗や民泊として活用されるケースが多くなり、当社にも多くのご依頼をいただいています。
アーリーアートでは京町家の修繕や改装だけでなく、実際に町家を民泊として運用している社員もいるため、町家を有効活用できる様々なリフォームをご提案しています。
この記事では、アーリーアートの建築・設計デザインに対する考え方や実例を元に、当社が考える町家リフォームとは何かをお伝えしたいと考えています。
「Less is More」モダニズム建築と日本建築の共通点

禅の文化を強く受けた日本建築は現代の建築と比較される部分もあると思います。しかし、当社ではどちらの建築にも共通する部分が多いと考えています。
それを表す言葉として近現代デザインの基礎を作り上げたバウハウスの3代目校長で建築家のミース・ファン・デル・ローエの「less is More(少ないことは、豊かなこと)」という言葉を常に頭に入れて仕事を進めています。
華美な装飾を施した豪華な建築ではなく、機能的でシンプルでありながら、心も身体も豊かにしてくれるモダニズム建築の中心的な建築思想は、日本建築の基礎的な建築思想とほぼ同じだからです。
だから私たちは、日本建築とモダニズム建築に共通する設計・建築デザイン思想を中心に、現代の暮らしに合わせた町家リフォームを進めています。
アーリーアートの町家リフォーム「3つの方針」

日本建築とモダニズム建築に共通する建築思想を町家のリフォームに応用しているアーリーアートでは、日本建築の利点を残しつつ、現代の生活でも使いやすい建築を目指しています。
それを実現するために、当社では3つの方針を建てて、町家リフォームをすすめています。
①町家の躯体や構造を活かす

最近、京都の繁華街などで見る町家の利用方法に少し疑問を感じることがあります。町家の躯体を大きく変えたり、玄関の構造を壊してガラス張りのショーウインドウを大きくとったりして、外観を大きく変えていることです。
私たちは、京都の街並みや文化を守るということも町家リフォームの目的のひとつと考えています。だから、大きく外観を変えたり、躯体をほぼ入れ替えたりするようなリフォームは極力しない。使える部分を可能な限り残して使い続けていく建築設計デザインを行っています。
この方針は、予算や工期がかさむこともありますが、京都の建築会社として守っていかなければいけない最重要項目だと考えています。
②暮らしやすさ、使いやすさを大切に

Youtubeなどで町家に住む方がいらっしゃるのを楽しく見ているのですが、住みにくさを理由に別の住居へお引越しされる方が多い印象があります。
風通しを重視して、湿気がたまりにくく、寒暖差が厳しい京都でも過ごしやすい京町家。しかし、昨今の夏の酷暑や冬の寒さに現代の日本人では耐えられないことも多いと思います。そこで、アーリーアートでは外観や躯体に影響がない内装に関して、京町家らしさを残しつつ、しっかり断熱材を入れたり、フローリングの床に変えるなど、現代の日本人でも快適で使いやすい町家を作り上げています。
古いものをただ守るだけでは、町家は守れない。使い続けてくださる方にとって快適で便利な空間を作り上げることこそ、町家を真に活かすことだと考えています。
③和の美しさを「機能デザイン」として取り入れる

モダニズム建築の考え方は「削ぎ落とし」と考える方もいらっしゃいますが、その解釈で設計・建築を追求していくと建築物はただの箱になってしまいます。しかし、そこに日本建築の思想や新しい素材などを取り入れることで、美しさと機能性を両立した設計・建築デザインを行うことができると考えています。
その設計・建築デザインコンセプトを、アーリーアートでは「機能デザイン」と呼び、当社が考えるあらゆる建築物に応用しています。
町家のリフォームでも、壁や窓、扉など、一見装飾にしか見えないものもあります。しかし、当社の設計・建築デザインでは、構造を支える役割があり、空間を活かしきる機能性を持たせています。機能を美しく見えるようにしている場合もあります。
美しさと機能性の両立は京町家のリフォームとしてはとても難しい課題ですが、京都の設計・建築デザイン会社として、妥協せずに取り組んでいきたいと考えています。
町家リフォーム、成功の秘訣は設計・施工の一体化
老朽化や過去の修繕の失敗、シロアリの食害。
古い京町家を店舗や住宅としてリフォームしようとすると、様々な困難が立ちはだかります。
それらを克服するために、アーリーアートでは設計から施工まで一貫して取り組む体制を整え、お客様や現場とのスムーズな連携や工期の短縮、予算に基づいた実現可能な建築設計デザインを行っています。
外観だけ見て設計図を引き、工務店任せの施工をする設計デザイン会社にはできない、設計・施工を一体化して取り組めるところが、当社の大きな強みだと考えています。
それでは当社がどのように町家のリフォームに取り組むのかをご紹介したいと思います。
最初に躯体の強度や状態をしっかりと調査
まず最初に取り組むのは、町家の状態確認です。
当社では既存の建材がそのまま使えるものはなるべく使う方針ですので、躯体のチェックは念入りに行い、設計期間中に何度も現場に足を運びます。
一見キレイに見えていても、柱が傷んでいたり、害虫の食害で強度が失われていたりする場合があります。また一見ボロボロの状態でも、丁寧に補修や補強をすることで、使い続けられる部材もあります。酷い場合だと、過去の建築や補修が杜撰で、本来あるべきところに柱や梁が無い場合もあります。
そういった町家の状況を、柱一本、梁一本から丁寧に確認し、町家全体の躯体を維持しながら、リフォームするために必要なことをリストアップしていきます。
躯体の状態確認と同時に行うのが、間取りの確認、採寸です。
町家は縦長の空間を襖や戸で細かく区切り、風通しと保温を調整できる仕組みになっています。しかし、現代は冷暖房を入れて快適さを調整する時代。店舗の場合は襖を取り外して大きな部屋にし、大きな空調をつける必要があります。また住宅の場合は断熱性と気密性を高めて温度変化を抑え、24時間換気機能を取り付けることも必要です。
町家の利用目的を考えつつ、間取りの確認・採寸をすることで、より快適で使いやすい町家へと進化させる基礎資料を作り上げていきます。
他にも階段の位置や角度、水回りの位置など多くのポイントをチェック。現状の問題点を把握して、
見積もりと設計の基本的な情報を綿密な調査によって入手します。
調査結果とお客様からのヒアリングを元に設計
現地調査と前後してお客様からお伺いした要望と建物の内容を照らし合わせながら設計をはじめます。
ご高齢の方がお住まいになる住宅では、なだらかな階段にしたり、段差をなくすバリアフリーに対応した設計を行います。また店舗の場合は、客席や商品ディスプレイのレイアウトを考えながら、従業員の動線の確保や作業のしやすさまで考えた設計を行います。
そういった店舗や住まいとしての重要な設計を、町家の保存ということも考えながら、時間をかけて多角的に検討していきます。使いやすさだけでなく、伝統的な街並みの保存まで考えた設計を行うことは、京都に拠点を置く設計・建築デザイン会社の使命だと考えています。
解体と同時に、残す資材を徹底的に清掃
設計段階でお客様の確認が取れると、いよいよ町家の解体にかかります。主に不要になる床や壁を解体処分し、柱や梁などの躯体を露出させてリフォームがしやすい環境を整えます。その後、柱や梁の補修箇所を確認しながら、躯体の清掃を行います。
100年間も建物を維持してきた柱や梁には埃や煤、アクなどが堆積してこびりついています。それらを丁寧に掃除し、取り除いてくことで、柱や梁を長持ちさせる効果があります。また天井板を外して梁を露出することができるようになり、天井高を確保することもできます。
当たり前のようで当たり前でない清掃作業を丁寧に取り組むことができるのも、当社の隠れた強みです。
古い建材と新建材を組み合わせ、見栄えを整える
次に取り組むのが、柱や梁、仕上げ材の補修や再生です。100年以上も使っている町家の建材は大なり小なり傷んでいる場合が多いです。そういう傷んだ部分をひとつずつ丁寧に補修していきます。
傷んだ部分だけを取り除いて、新しい建材を伝統工法の「つぎ」を応用して一本の建材にする場合が多いのですが、躯体を維持できないような傷みを伴う建材は、新しいものと丸ごと入れ替えます。
内装で隠れる建材ならそのままで良い場合もあるのですが、露出して目立つ場合は、古い建材と馴染むように色のついたオイル塗料を塗布して古い建材と合わせても違和感がない風合いに整えていきます。
町家の保存再生をする時は、見た目の違和感も徹底的に排除し、視覚的にも建築物の歴史を感じられるようにしています。
京都の景観を守る町家の外観デザインを保つ

町家の外観を大きく変更し、店舗として利用するように作り変える設計デザイン会社や工務店も多いと思いますが、当社では極力外観を活かした設計・建築を心がけています。そこには大きく分けて2つの理由があります。
ひとつは京都の街並みや景観を守り再生させたいからです。
先の大戦で空襲を受けず、多くの古い木造建築が残っていた京都ですが、多くが取り壊され、便利で快適な現代建築に置き換わっています。そんな中で残っている町家は欠かすことのできない貴重な建築物で、町のシンボルにもなりかねない貴重な存在です。だから住む人が変わったり、店舗へと役割が変わったとしても、外観は極力守らないといけないと考えています。
もうひとつは地元住民の皆さまとの関係性です。
どの地域よりも長い歴史を誇りに思い、自分たちの文化を守りたいと考えている人々が多いからこそ、外観の変化で関係性が良好に保てない場合もあるからです。長く住み、長く商売をしていくためには、周辺住民の皆さまにも気に入っていただける設計・建築を目指さなければなりません。
外観をどのように維持するかですが、長年の風雨に耐えてきた分、汚れや痛みがかなりあります。柱や梁の掃除だけでは再生できないことが多いです。そこで木材部分は塗装し、白壁に関しては左官職人が丁寧に塗り直します。また新しい建材に差し替えた部分も、町家の雰囲気を失わないように加工してます。
新旧の技法を合わせて、古い外観を美しく再生させていく工法が、アーリーアートにはあります。
奥行きを利用する
間口が狭く奥行きが深い独特の構造を活かしてこそ、町家のリフォームは成功すると考えています。

例えば上記写真は当社が担当したヘアサロンですが、町家の縦長空間を区切らず使い、シンメトリーにスタイリングチェアを配置。庭まで見渡せるようにすることで、ゆとりと居心地のよさを感じていただける空間に仕上げています。

こちらは町家ではありませんが、町家の跡地に建てられた奥行きが深い鉄骨造の物件にある鉄板料理店です。奥行きの深さを利用して、オープンキッチンを複数配置、ライブ感ある調理を目の前でお客様に楽しんでいただけるようにしています。しかも一番奥を広々とした個室にすることで、特別感も演出することができています。
当社には町家の奥行きを活かす「様々なアイディア」の蓄積があるため、あらゆる業種やお客様のご要望にお応えすることができます。
広さを感じさせる
町家で日常を過ごすと、日々気になってくることが間口の狭さからくる圧迫感です。そこでアーリーアートでは、町家をリフォームする際に、空間を広く見せる工夫を多く取り入れています。

例えば、こちらの飲食店では壁一面を鏡にしています。これにより部屋が倍の広さのように見える効果が生まれ、空間にゆとりを感じられるようになります。
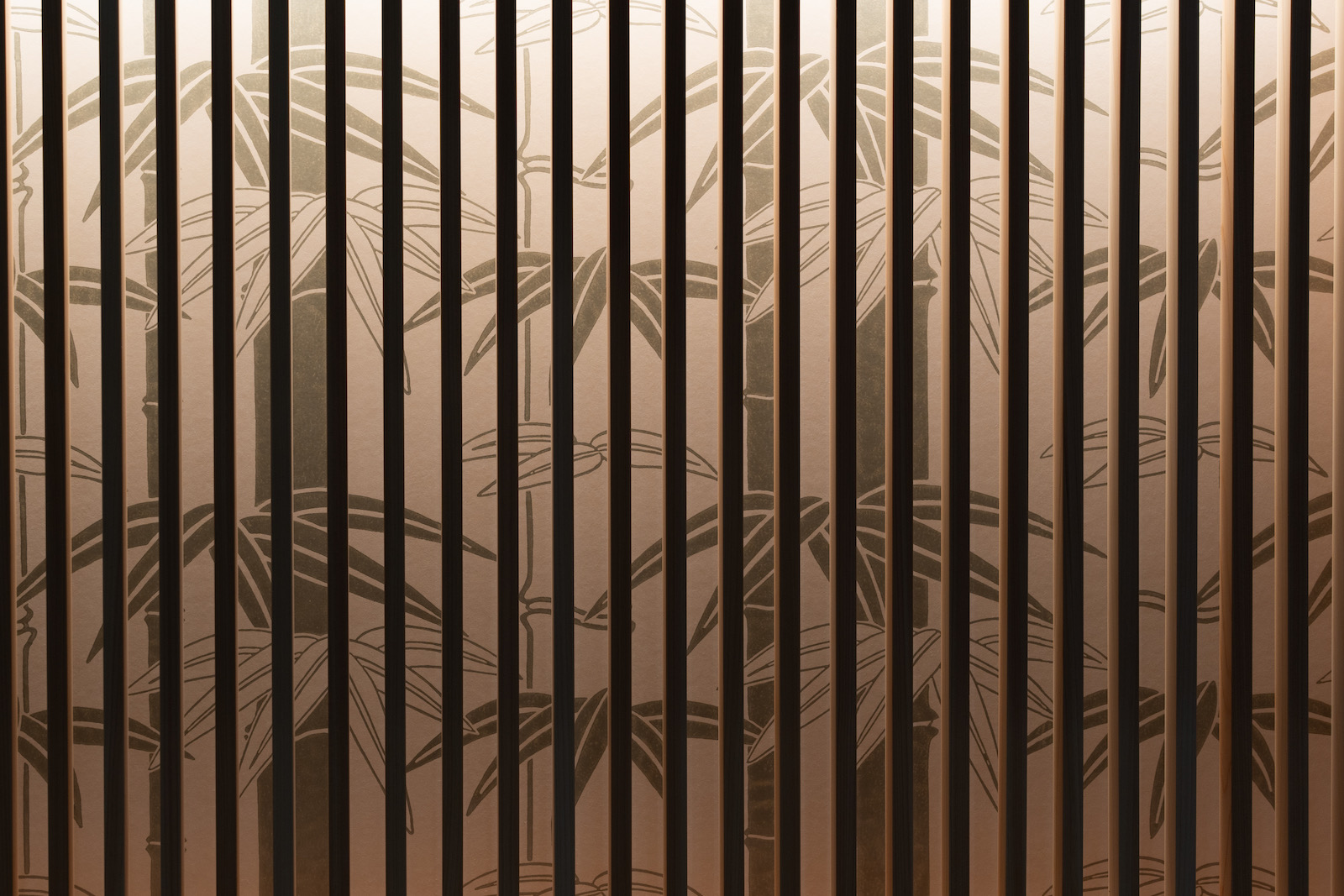
こちらも同じ飲食店ですが、壁面に格子をつけ、その奥に竹の襖紙を貼り付け、照明で演出しています。これはただの和風演出と思われる方もいらっしゃいますが、実際には格子と襖紙の間に空間を作ることでそれ以上の広さを感じさせる実用的な効果があります。まず格子があることで、人はその向こうに何かがあると認識します。そこに襖紙と光の演出があるとさらに奥には空間があると感じます。襖紙の柄を竹にしていることから、竹林をイメージすることもできます。
このように、一見、演出的なデザインに見えるものでも機能的に配置することで、広さを感じ、すっきりとした空間を演出することができます。
これも当社が考える「機能デザイン」のひとつです。
天井高を確保しながら、梁を美しく魅せる
町家の欠点として、天井の低さがあります。昔の日本人の身長に合わせているため、現代の日本人には低すぎるのです。そこでアーリーアートでは天井板を外して梁を露出させることで、天井を高くして、現代の日本人でも暮らしやすい町家を目指しています。

上の写真は町家を改装したレストランですが、天井だけでなく2階もなくして梁や柱に洗いをかけ、キレイに塗装することで、町家らしさを活かしながら、和モダンと言われるオシャレな空間を作り出しています。

こちらの写真は住宅として使われている町家のリビングです。ここでも天井板を外して梁を露出させることで天井高を確保しています。また梁の上にしっかり天井と2階の床を作っているため、スペースのムダもありません。
このように梁を美しく見せる町家リフォームは、設計と施工を一体化して取り組める当社ならではの得意分野でもあります。
現代的な部屋に伝統的な建具を入れる
店舗でも住宅でも、内装は新しくしていくことが多いです。床はフローリング、壁はクロスで仕上げることも多いですが、どこかに必ず、町家らしさや和の趣がある建具などを入れられるように工夫しています。

上の写真は、階段下の物置スペースの扉に舞良戸(まいらど)と言われる日本の伝統的な建具を新たに設置しました。

こちらのバーカウンターは、土や石を積み重ねて壁を作る版築(はんちく)という伝統的な建築技術で作り出しました。このように伝統技術で作成したものにバーカウンターとしての役割を与えて露出させ、室内のデザイン要素として取り入れることも、アーリーアートが考える機能デザインのひとつです。
最新の設備で、便利に快適に
当社では町家を自己満足な博物館にしない。人々に使っていただくことこそ、町家の役目を果たせると考えています。そこで、店舗でも住宅でも最新の設備を上手く取り入れています。

上の写真は天井から電動で降りてくる物干し竿です。町家は日当たりが悪かったり、物干しスペースが小さかったりする場合が多く、洗濯物を干す時に困ることが多いです。そこで、このような電動で収納できる物干しを取り付けることで、日々の生活も部屋干しも快適に行えるようにしています。

こちらのヘアサロンではスチームを使ったヘアスパができる機器を床に取り付けられるようにしています。床下に配管や配線を隠すことで、町らしさを維持しつつ、最新設備を使えるようにしています。
このように町家らしさを保ちながら、使う人、住む人が快適な町家リフォームを目指しています。
季節の飾りを楽しむ、趣ある遊び心

町家を守ること、使いやすさや快適さを考えること。あらゆることに目配せをし、設計・建築デザインをしているだけでは、どこか日本人の心の安らぎを置き忘れてしまうことがあります。そうならないように、日本らしく四季を楽しみ、季節の飾りや花を飾るスペースを設けることにしています。
例えば上の写真は玄関のスペースに作った小さな洞床です。
本来であれば床の間の代わりに和室に取り入れるべきスペースですが、玄関から入った正面に配置し、お客様を迎えて一番最初に目に飛び込んでくるフォーカルポイントを作りました。床から離れて生活する現代の暮らしに合わせて、高い位置に設置。祇園祭にはお祭りの飾りを、お正月には千両を、季節に応じた飾りを設えることで、心の安らぎが生まれる空間を作っています。
「古い」を守るために、「新しい」を取り入れること

この記事ではアーリーアートが考える町家リフォームについて実例を上げながらご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。
古い町家を維持しながら有効活用することは、とても素敵なことですが、同時に難しい仕事でもあります。
当社では長年の経験と技術力はもちろん、設計から施工まで一体化して取り組む体制で多くの町家を再生してきました。古い建材や文化の本質をしっかり守りながら、新しい工法や考え方を取り入れ、現代の日本人が使いやすい町家を目指す努力を、日々積み重ねています。
ここまで長い文章をお読みいただき、ありがとうございました。もしこの記事をお読みになって、町家をリフォームしてみたいとご興味をお持ちになった方は、ぜひ一度、お気軽に当社へご相談ください。
素敵な町家のリフォームを、素敵な京の街づくりを、お客様と共に行っていきたいと思っています。

